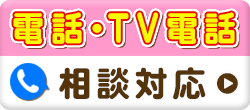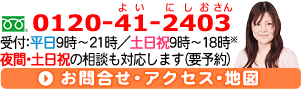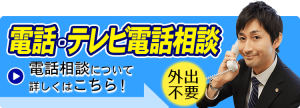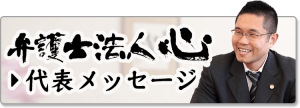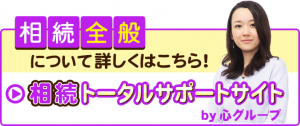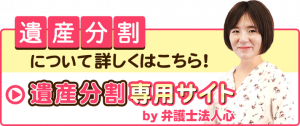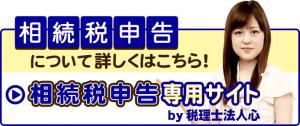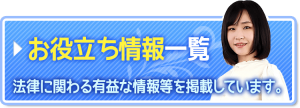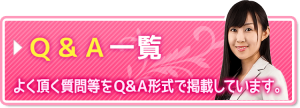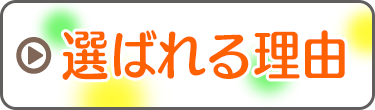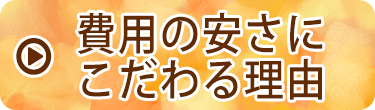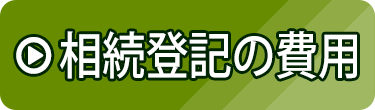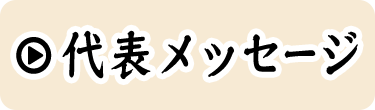相続登記の義務化!改正内容と罰則【2024年版】
遺産分割協議などを経て当該不動産を相続する人が決まった場合には、被相続人名義の登記から相続人名義の登記に変更することになります。これを一般に「相続登記」といいます。
しかし、土地の価値が低い場合などには、相続登記の費用負担や手間を嫌い、相続登記を行わない人も少なくありませんでした(いわゆる「相続負動産」)。
相続登記を放置している間に次の相続が開始するなどして、不動産の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも過去には多かったのです。
所有者不明の不動産が増えることによって、所有者の探索に多大な時間と費用を要することになり、不動産の円滑かつ適正な利用に支障が生じるようになりました。
このような問題の対策として、政府は、土地について相続登記を義務付ける内容で不動産登記法の法改正を行いました。
今回は、2024年4月に施行された相続登記の義務化についてわかりやすく解説します。
1 相続登記の義務化はいつから?
相続登記の義務化については、2024年4月1日から施行となりました。
現時点では、相続登記が未了となっている不動産があったとしても直ちに罰則が適用されるというわけではありません。
しかし、現時点で何世代にもわたって相続登記が放置されている不動産がある場合、適切に相続登記を行うためには、相当な時間と労力を要することになります。
弁護士が相続の相談を受ける場合に、この相続調査に多大な時間と労力を必要とし、事案解決がなかなか進まない事例も多くみられます。
現状に合致した登記名義としておくことで、今後の相続登記の負担は軽減されることになります。
義務化を受け、専門家に相談しながら現状に即した登記内容にしていくようにしましょう。
2 相続登記の義務化の改正ポイント
⑴ 相続登記の義務化
土地の所有者が亡くなり相続によって当該不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知ってから3年以内に、所有権の移転登記申請をしなければなりません。
また、相続登記後に遺産分割を行った結果、法定相続分を超えて不動産の所有権を取得することになった場合には、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転登記申請をしなければなりません。
相続による不動産取得後3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料となります。
⑵ 相続人申告登記の創設
遺産分割協議が長期化しているような場合には、相続開始から3年以内に相続登記ができないこともあります。
そのような場合には、新たに創設される相続人申告登記を利用できます。
相続人申告登記とは、法務局において、自分が相続人であることを申告することによって、相続登記の義務を履行したものとみなす制度です。
相続人申告登記をすることによって、申請をした人の氏名および住所などが登記に記載されることになります。
ただし、相続人申告登記も、その後に遺産分割協議が成立し、不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転登記申請をしなければなりません。
⑶ 遺贈による所有権移転登記手続きの簡略化
従来は、相続人に対して遺贈がなされた場合でも、相続登記をする場合には、他の相続人と共同申請をする必要があり、遺贈の内容に不満がある相続人がいる場合には、共同申請の協力が得られず、相続登記が困難になるという事情がありました。
なお、この共同申請というのは思った以上に難しく、特に相続争いをするような事案では非常にハードルが高いことが多いです。
そこで、改正案では、相続人に対する遺贈については、登記権利者(受遺者)が単独で登記申請できる内容に変更されました。
⑷ 法定相続分での相続登記がされた場合の簡略化
改正後は、相続登記をした後に遺産分割を行った結果、法定相続分を超えて不動産の所有権を取得することになった場合には、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転登記申請をしなければなりません。
ただし、法定相続分で相続登記がされている状態で以下の登記をする場合には、登記手続きを簡略化する(更正の登記による)ことが認められます。
これまでは、他の相続人との共同申請を求められていましたが、登記権利者による単独の申請が可能とされています。
単独申請が可能となるのは、実務上、共同申請が非常に難しいことを考慮されていることの表れであると考えられます。
・遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
・他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
・特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
・相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
⑸ 所有権の放棄(国庫への帰属)が可能になる
意外に思われるかもしれませんが、民法には所有権の「放棄」に関する規定がありません。
そのため、例えば自分が所有する土地があまり活用できず買い手がつかない場合であっても所有者であり続けます。
しかし、相続によって得た土地についても所有し続けることになると、かえって管理の杜撰な土地が増えることにも繋がりますし、相続人にとっても負担になります。
特に「負動産」といわれる不動産を譲り受けたような場合にはこれが顕著です。
そこで、相続及び相続人に対する遺贈によって土地を取得した所有者は、その所有権を国庫に帰属させることの承認を求めることができるようになりました。
これには法務大臣への承認申請が必要ですが、その土地が一定の例外事由に該当する場合を除いては、国庫への帰属が原則として承認されることになります。
3 相続登記の申請義務違反への罰則
相続登記を義務化することに伴い、相続登記の申請義務違反には罰則が適用されることになります。
罰則の内容としては、相続登記の申請義務のある人が正当な理由なく相続登記の申請期限内に申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられるというものです。
ここでいう「申請義務のある人」というのは、以下の2パターンです。
・上記の2⑴でご説明した不動産の所有権を取得した人
・上記の2⑵でご説明した相続人申告登記を行った後、不動産の所有権を取得した人
なお、過料は、行政上の義務違反に対する罰則の一種ですので、刑事上の刑罰である「罰金」や「科料」とは性質が異なります。
そのため、過料に処せられたとしても、前科になるわけではありません。
4 義務化された相続登記は弁護士に相談を
相続登記の義務化により、相続人にとっては手続きの負担が増加することもあるでしょう。
しかし、相続登記は民法上の対抗要件とされており、自己の権利を守るために重要な手段です。
また、相続登記の義務化以外にも登記手続きの簡略化も併せて改正されましたので、必ずしも大きな負担になるとはいえません。
現時点で、相続登記未了の不動産を所有している方は、早めに現状に即した登記内容となるように整理しましょう。
相続登記については、当法人の弁護士にお気軽にご相談ください。